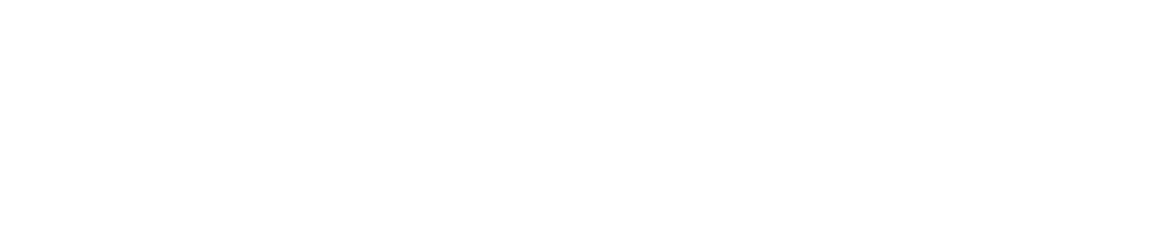子どもたちの安全を守る
送迎バス置き去り事故を防ぐための優れた取り組みから学ぶ
全国には4万台以上の子どもを幼稚園、保育園、こども園などに送迎するバス(以下「園バス」とします)が走っています。毎日、朝と夕方、何万人もの子どもたちが安全に通園できているのは、保育園・幼稚園の先生方の真摯な努力があってのことです。
各園では、子どもたちの安全を守るために様々な工夫を重ね、大切に育んできた取り組みがあります。しかし、そうした優れた実践は、なかなか他の園には伝わりにくいものです。
このWEBサイトは、園バスに子どもを置き去りにする事故を防止するために実践されている優れた安全対策を集め、広く共有することを目指しています。ここに集められた事例の1つ1つには、子どもたちの命を守りたいという現場の強い思いが込められています。
どうか皆様の園でも、これらの実践例を参考に、それぞれの実情に合わせた形で活用していただければ幸いです。子どもたちの安全を守る取り組みを、共に支え合っていきましょう。
調査概要
関西地域の105の幼稚園・保育園・こども園に対して、置き去り事故防止を始めとする園バス運用上の安全対策について、ヒアリング調査を行いました。収集された事例の中から、特に優れていると思われる取り組みを分析し、安全管理の専門家による評価を加えてまとめました。
園バスの安全確認 – 具体的な事例の前に
置き去り防止の優れた取り組みをご紹介する前に、多くの園で実践されている基本的な安全確認の取り組みについてお伝えします。これらは子どもたちの安全な通園を支える重要な土台となるものです。まずは、皆様の園での取り組み状況を確認してみましょう。
1.複数人での確認
保護責任は保護者、添乗者、職員と次々に移るため、引継ぎ時の確認が重要です。責任の所在を明確にすることで、置き去り事故の防止につながります。
2.正確な人数把握
3.見守り体制の工夫
国土交通省が義務付けた置き去り防止装置について、調査園での設置率は100%でした。
各園の設置方式の内訳
降車時確認式:83%/自動検知式:7%/不明:10%